この記事は約5分で読むことができます。
吃音当事者の石黒栄亀と申します。 幼いころから吃音を抱えていましたが、年齢を重ねるにつれて「頭にある言葉が口から出てこない」という出来事が子供のころより頻発するようになりました。今回は、そんな私が主治医の紹介で吃音外来にかかった時のことをお話します。
子供のころから「声」と「話し方」はコンプレックスの1つだった。

子供のころから「声」と「話し方」はコンプレックスの1つとして、今もあり続けています。
それでも、まだいろいろ無自覚な頃は、自分が違っていることにあまり意識が向いていなかった気がします。
しかし、思春期を迎えた小学生の終わりか中学生のはじめの時、周りが他人や自分に意識的になる時期がきました。
「オマエ、なんでそんなしゃべり方なの?」「コイツの声が嫌い」というセリフを面と向かって言われたことがありました。
今となっては、どれくらい言葉に課題があったのかは、はっきりと覚えていないというのが正直なところです。
ただ「たまに言葉がすっと出てこないな」「言い始めの言葉を繰り返すことがあるな」という体験を何度かしていました。
しかし、その時にはそれがその後の人生にかかわる大きなことになるとは予想もしていませんでした。
話すことが必須になるにつれて、うまく話せないプレッシャーは大きくなるばかり…

その後、高校、大学、大学院と進むにつれ、適切に話すことが必須の環境になりました。
それでも、話すことがまったく上達しないどころか、うまく話せないことへのプレッシャーは大きくなるばかりでした。
研究者の末席を汚すようになっても、毎回汗びっしょりでプレゼンテーションをこなし、焦るほど言葉はもつれ、壇上から質問者の苦笑いを何度も見て、最後は時間切れのベルに救われてきました。
そうこうしているうちに、「頭にある言葉が口から出てこない」という出来事が子供のころより頻発するようになりました。
口と喉が固まり、声帯を震わせるための息さえ出てこない感じでした。
そして、息が出るときには口唇が自由にならず、同じ言葉の頭を繰り返す感じがしました。
家族からも「もっと落ち着いて話したら?」と言われるようになりました。
会議で話し始めた時、語頭の繰り返しが止まらなくなった。

そしてある日のこと。それは突然訪れました。
その日は朝から誰かと話すことはなく、開催された会議の場がその日に初めて話す機会でした。
会議で話し始めた時、語頭の繰り返しが止まらなくなってしまったのです。
その場にいた人が全員怪訝な顔で私を見ています。
しかし、話せば話すほど言葉は吃り、ある時には出なくなることを繰り返すようになりました。
実はそれが起こる数か月前から、私は心療内科に通うようになっていたため、すぐに主治医にそのことを話しました。
話したといっても、言葉は相変わらずでした。何を喋ろうと吃らずに喋ることなど不可能な状態でした。
主治医の先生は薬の影響かもしれないということで、処方されている薬の1つを変えてくれました。
しかし、結果は変わりませんでした。
ある時、主治医の先生が私に静かに言いました。
「私は吃音の専門家ではないので、耳鼻咽喉科に診てもらってください。」
私はその足で以前鼻炎でかかっていた耳鼻咽喉科に向かいました。
久々に相対したその先生も、私の様子をみて一言「悪いけれど、私も吃音は専門外なんだ。だから申し訳ないけど何もできないんだよ」
何もできなかった証明のように、わずかな会計をして医院を出ようとしました。
そのとき、受付の人が急に私を呼び止めました。
「先生から連絡先を聞いておいてくれ、後で連絡するとの伝言です」
私はそれが何を意味するのか、全く分かりませんでした。
主治医に吃音外来を紹介してもらった。

数日後、その先生から直接スマホに電話がありました。
「自分の後輩に、吃音外来をやっている医師がいる。話したらそちらに繋げてもらって構わない」ということでした。
3か月の予約待ちの後、特急列車に乗って自宅からやや離れた都市の病院へ出かけました。
電車をさらに乗り継いで、病院で受付を済ませ、吃音外来の前で静かに待っていました。
名前を呼ばれて中に入り、もうそれが当たり前のようになっていた連発と難発を繰り返しながら、先生の質問に答えていきました。
先生は少し黙って、スマホのメモ機能、読み上げ機能、メトロノームアプリなどを教えてくれて、場面に応じて使い分けるといい、と言いました。
40分ほど話して「次は3か月後にまたお会いしましょう」と予約を入れ、私は診察室を後にしました。
正直ちょっと肩透かしな気分でした。
それでもせっかく大きな街に久々に来たので、普段買えない物を買ったりして、ちょっと楽しんで気分を変えて、帰宅する特急に乗りました。
「先生、私はこのままなんですか?」 子供のころからの「何か」に1つ片が付いた。

3か月後。再び吃音外来の診察室の中で、先生と静かに話をしました。
私の吃音は相変わらず派手で、3か月前から何も変化がありませんでした。
先生は「普段、初めての人にお話しするときにどうしていますか?」と聞いたので「私は言葉が不自由ですので、わかりづらかったら遠慮なく聞き返してもらって構いません、と言っています」と答えました。
先生は少し黙ってうなずき「これで終わりにしましょう。私のアドレスをお教えしますので、困ったらいつでも連絡いただいて構いません」と言いました。
私はここで気づいたのです。自分の言葉はもうこのままなんだということに。
それでもお礼を述べて診察室を出る間際「先生、私はこのままなんですか?」と聞いてみました。
先生はただ曖昧に微笑んだだけです。
多分、先生にとっての私に対する吃音外来の仕事は、私が吃音を一生受け入れていくことができるかどうかの確認だったのでしょう。
私は実はそんなにショックでもなく、どこか淡々としていました。
子供のころからの「何か」に1つ片が付いた気持ちがあったのかもしれません。
私はまたせっかく大きな街に来たのだから、という理由で帰りにいろいろ買い物を楽しんで、夕暮れ近く帰りの特急に乗りました。(石黒栄亀)



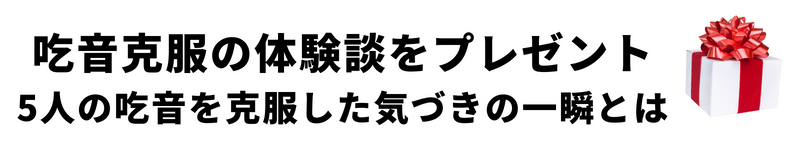

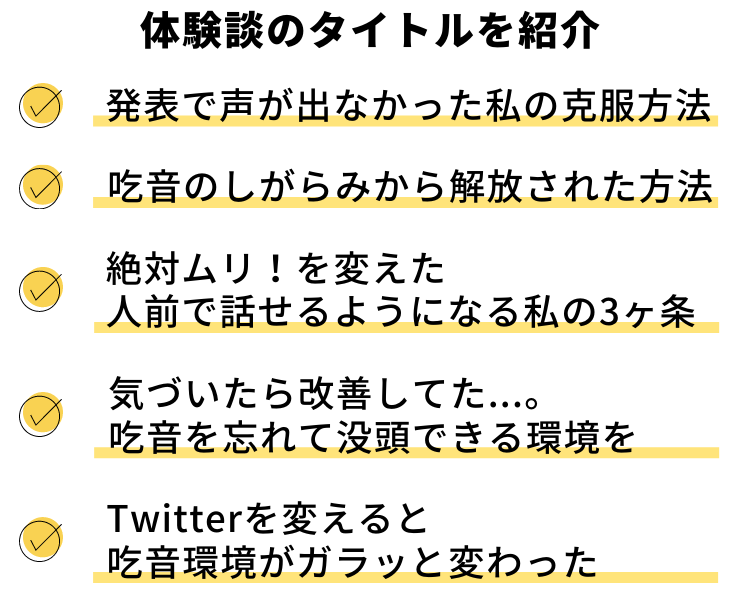















この記事へのコメントはありません。