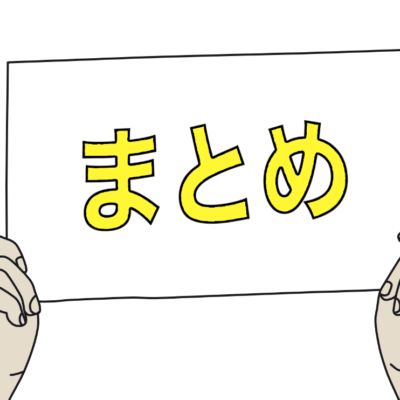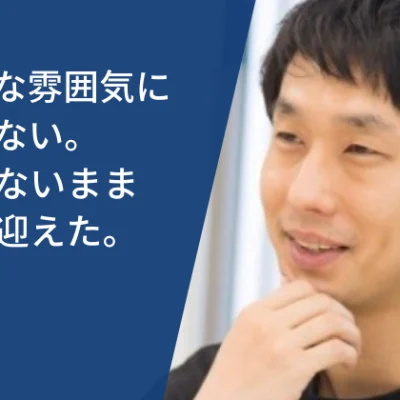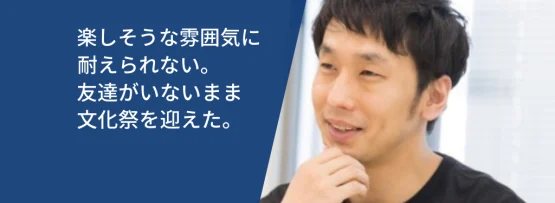1、症状

吃音(きつおん)、吃り(どもり)は話し言葉が滑らかに出ない発話障害のひとつです。
滑らかに話せる時もありますが話せない時もあり、症状に波があります。
吃音を持つ人は日常生活で無意識に滑らかに話せるように工夫をしていき、言葉が出にくいときはその動作を伴って発話することもあります。
例えば、話す前に体を動かして勢いをつけたり、言葉の最初に「あのー」や「はい」などその人が言いやすいことばをつけるなどといったことなどが挙げられます。
吃音は大きく分けて3つの症状に分類されます。
【主な3つの症状】
①難発
「——–っありがとう」と言う「難発」。言いたい言葉の最初の音が出にくい症状。
なんとか発声しようとのど等に力が入り、最初の音だけ大きくなったりする場合もある。
②伸発
「あ―――りがとう」と言うような最初の音を引き延ばす症状の「伸発」。
言葉の最初の音から次の音にうつるまでの時間が長く、最初の音が引き延ばされるのが特徴。
③連発
「あ、あ、あ、ありがとう」「あり、あり、ありがとう」同じ音を繰り返す「連発」
初めの音や言葉の一部を何回か繰り返す話し方が特徴の症状。
2、割合・罹患率
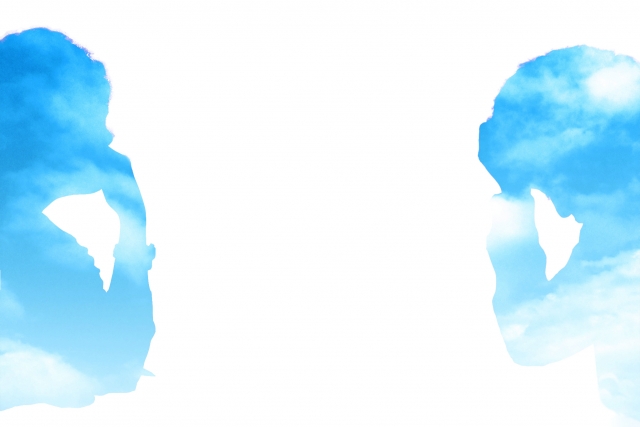
罹患割合は調査によっても前後するため、正確な数は研究中です。
ただ目安として2~4歳で5~8%前後が吃音をもっているといわれています。
その内、7~8割ぐらいが自然に治るといわれています。
成人では1%は吃音があるという調査結果もあります。
また、女性より男性の割合が多く、男性の方が、女性を比べて3~5倍多いという報告もあります。
3,原因

はっきりした原因は長らく不明で、研究中です。
ただ約7割は生まれ持ったものといわれているので、決して親御さんの育て方に問題があるわけではありません。
4,望ましい対応

では吃音の症状がわかったところで、どのように接することでお互いが気持ちよく関係を築けるのでしょうか。
望ましい接し方をご紹介していきます。
- 話し方ではなく、話の内容に注目してゆったり聞く。
- 吃音症状があっても、他の得意なことに目を向ける。得意なことを褒めたり、活かせる場を提供する。
- 無理解な人へは、吃音に対する正しい知識を説明する。
5,望ましくない対応

逆に吃音者にとって望ましくない対応をご紹介したいと思います。
- 「落ち着いて」「ゆっくり話して」などの不用意なアドバイス
(既に本人はどこかで言われて試しています。話す速度によってスムーズに話せるようになるなら、とっくにそうしているでしょう。) - 「しっかり話せ」などの理不尽に怒る。
(しっかり話せるものならとっくに話しています。) - 「もう一度言ってごらん」と言い直させる。
(何度練習しても言いづらい言葉は変わりません。むしろ言いにくい言葉をもう一度言わされることで苦痛を感じることもあります。)
6,まとめ
まだまだ世の中には理解が進んでいない吃音という障害。
笑われたり、バカにされたり、「しっかり話せ」と怒りをぶつけられる場面も、残念ながらまだまだ存在します。
NPO法人日本吃音協会(SCW)では、そんな現状を変えて吃音をもつ人が生きやすい社会をつくるために活動しています。